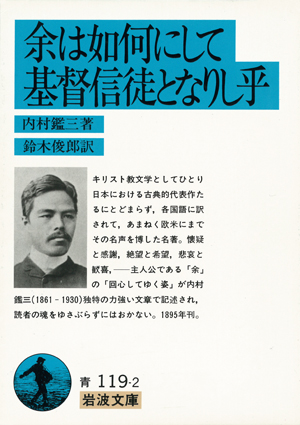図書館だより
敬和学園大学 図書館だより(2008年9月号)
学生に推薦したい本 (共生社会学科准教授 青山良子)

「なぜ、『死』について考える本を推薦するのか?」
青春まっただなかの学生の皆さんに、なぜ「死」について語られたこの本を紹介するのかと不思議に思われるかもしれません。
私たちは、どんな人も、よりよく生きることを望んでいるはずです。いかに生きるかについて真剣に考えるためには、「死」について考えることを抜きにはできないと思っています。「死」について考えることは、「生」について考えることであり、それは人間について、そして自分について深く考えることにつながると思っています。
死について考える上で、私は今から30年ほど前に、衝撃的な本と出会いました。それが、このキューブラー・ロスの「死ぬ瞬間」です。個人的な体験として身近な人の死に直面し、仕事の上でも死から逃れられない難病の子どもたちと関わることになった頃のことです。
この本の出会いと、これらの体験が、私に「死」について考えることは「生」について考えることだということを実感させてくれました。
「『死ぬ瞬間』には、何が書かれているのか?」
1969年に、当時43歳の精神科医であるキューブラー・ロスは、「死ぬ瞬間(On Death and Dying)」を発表しました。「死ぬ瞬間」は世界的ベストセラーとなり、今でも多くの人に読み継がれています。死にゆく人々の心境を克明に記し、死を真正面から見据えたその内容は、社会に大きな衝撃を与えました。
キューブラー・ロスは多くの死にゆく人々との対話をとおして、死にゆく人々の心の動きを、否認→怒り→取り引き→抑うつ→受容の5つのプロセスとして明らかにしました。
その内容を、簡単に紹介しましょう。
「否認」について、ほとんどといっていいほど、患者はこの否認を行う。自分の病気は何かの間違いだと考える。「われわれはしょっちゅう太陽を見ていることができないように、われわれはしょっちゅう死に立ち向かっていくことはできないという言葉があるように、こうした否認は彼らの自然な対処療法である」といい、「患者にとって否認は常に必要」であり、一番の初期にはそれは特に必要であると強調しています。
「怒り」は、否認という段階がもはや維持できなくなると、怒りがこれに取って代わる。他の人ではなくなぜ私が…という怒りであり、この怒りはあらゆる方向に向けられるため、まわりの人々は患者を避けたいという気持ちにもなるといいます。
「取り引き」の段階とは、この現実から逃れる方法として何かにすがろうとする心理的状態で、否認や怒りと同じように患者にとって助けとなるといいます。
「抑うつ」は、何もしたくなくなる状態で、この時期は、励ましより、患者が悲しみを表現することを許してやること(話を聞くこと)、そばにいることだけでもよいといいます。それにより、次の段階である受容ができやすくなるともいっています。
「受容」は、自分が死にゆくことを受け入れる段階で、自分の運命について抑うつもなく怒りも覚えない段階に達するといいます。しかし「受容を幸福の段階と誤認してはならない」ともいっています。
キューブラー・ロスは、「これらの諸段階をとおして常時維持していく一つの流れは希望ということである」といい、「患者が希望を持ち続けるためにうそをつかねばならないということではなく、ただ私たちが患者と希望を分け持つという意味である」といっています。そして、そのためには「問題を避けることのほうがはるかに有害だと私は確信している」といい、「患者は、分かち合いたいのだ」と強調しています。
「『死ぬ瞬間』の果たした役割はなに?」
「死ぬ瞬間」は世界的ベストセラーとなり、死を真正面から見据えたその内容は、社会に大きな衝撃を与えたと前述しましたが、社会にどんな影響を与えたのでしようか。
なによりも、死にゆく人々が死について語ることを望んでいるという事実から、「死」から目をそむけたり隠したりしないことの大切さが明らかになったことです。それは、患者本人に対してだけでなく、家族や、医師をはじめとする死にゆく人にかかわるすべての人に対していえることでした。しかし、患者と死について話すことに最も抵抗したのは医者だったそうです。医学にとって「死」は敗北と考えられていたからです。
患者が自分自身の「死」について語ることで、医療の分野での「死」の捉え方が変わっていきました。簡単にいえば「死」を先に延ばす医療から「生」を支える医療への変化とでもいえると思います。ホスピス医療などの発展がその典型といえます。
「『五段階』を知ることだけが重要なのではない」
キューブラー・ロスの提唱した死の受容への五段階は、すべての人にあてはまるわけではないことは確かですし、多くの批判があることも確かです。しかし、死にゆく人と関わるうえで、この五段階についての知識は、私たちに多くの示唆を与えてくれたことも事実です。しかし、キューブラー・ロスは最後の著書でこんなふうに述べています。「最後にあたって、読者に伝えたいことがある。…(略)…『五段階』を知ることだけが重要なのではない。生の喪失だけが重要なのではない。重要なのは生きられた生である」と。
「最後のレッスン」
死の専門家といわれたスイス生まれの精神科医は、その生涯で1万人を超える死にゆく人々と寄り添い、死の不安におののく人々の気持ちを受けとめ、人生の最後を安らかなものにできるよう力を尽くしてきました。
「死」を、一人称の死、二人称の死、三人称の死ということばを使ったのは柳田邦男だったと思いますが、キューブラー・ロスは、これまでは、多くの三人称の死にかかわってきたといえます。そして、最後に、キューブラー・ロスは自分自身の人生と死を見つめて、まさしく一人称の死について語ります。キューブラー・ロスは、2004年8月24日午後8時10分に、78歳でその生涯を閉じました。その姿を、2005年にNHKが、ドキュメント「最後のレッスン」として伝えています。
「死は人生で最もすばらしい経験にもなりうる。そうなるかどうかはその人がどう生きたかにかかっている。私は死の床にあるひとに教えを請うてきた」とキューブラー・ロスは「死ぬ瞬間」の中でも述べていますが、そのドキュメントは、自分自身の「死」を対象とした、まさしく一度きりの「最後のレッスン」だったといえます。
興味のある人は、キューブラー・ロスの最後の著書「永遠の別れ ―悲しみを癒す知恵の書―」も、ぜひ手にとって読んでみてほしいと思います。
最後にもう一度くりかえします。よりよく生きるために、青春のこの時期に、一度は立ち止まって「死」について考えてみてはどうでしょうか。