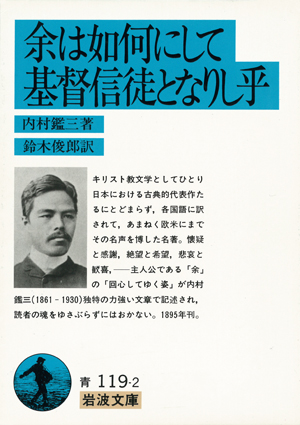図書館だより
敬和学園大学 図書館だより(2010年8月号)
学生に推薦したい本 (英語文化コミュニケーション学科准教授 山崎由紀)

一年生の基礎演習で学び始めた頃から、皆さんは大学時代にたくさんの本と出会って欲しいという先生方の言葉を聞き続けていることと思います。読書は、自分以外の人生を追体験できる数少ない機会であり、他者に思いやりを持ちたいという気持ちを「絵に描いた餅」としないためにも、自分以外の人生や考え方に数多く触れることは、重要なことでしょう。他者に思いやりを示すだけではなく、自分の考えを深く豊かにし、これからの人生を充実させるためにも、今持っている自分の考え方だけでは足りないことに、いずれ皆さんは気づくでしょう。本は、新しい考え方との出会いの機会ともなります。その出会いの経験はやがて、皆さんの将来の可能性を切り開いていくことでしょう。
皆さんにたくさんの本と出会って欲しいと書きましたが、反面、私自身は書店に平積みにされた本やテレビの情報番組で紹介される「速読のすすめ」には大きな疑問を感じています。むしろ、反発と言ってもいいかもしれません。ある情報番組に紹介されていたのは、本の行を上から、あるいは下からどんどん眺めて、見える文字から物語を自分の心の中で再構築して、筋を理解していくというものでした。多くの情報を、短時間で自分の中に取り込む必要がある時には良い方法でしょうが、これで作者が一文字一文字選び抜いた言葉を本当に味わうことができるでしょうか。作者が自分の命や人生をかけて紡いだ文章に託された思いや心が、私たちに伝わるでしょうか。私はそのような疑問を感じます。
ここに、『読むことの力』という本があります。NHKで放映されている「Jブンガク」という5分間の番組を担当中のロバート・キャンベル先生が編集されました。キャンベル先生は2003年度に、大学一年生のためのチェーン・レクチャー(毎回異なる講師が講演する授業)を企画しましたが、それを後に一冊の本にまとめたのがこの『読むことの力』です。アメリカのニューヨーク州出身のキャンベル先生は、もはや外国の方の日本語とは思えない豊富な語彙を武器に、私たち日本人が気づかなかった日本文学の魅力を、ご自身が深く学ばれた日本の価値観と、ご自身の内にあるアメリカ生まれの価値観とから生まれた、キャンベル先生独自のしなやかで新しい価値観を持って、私たちに紹介するというユニークな仕事をされています。
この本の帯には「本という他者とケンカする愉しみ」というコピーがつけられています。無論、決別のためのケンカではありません。「どうして自分にはこの相手が理解できないのだろう。なんと、とっつきづらいことだろう。」本ではなく、人間相手でも、このような感情を持つことはあるのではないでしょうか。ですが、心のどこかにその相手を理解したいという気持ちがあるならば、時に理解できない苛立ちをストレートにぶつけて、自分の無知もさらけ出しながら、取っ組み合いのケンカをする必要があることもあるでしょう。本も同じことです。本を読むという行為は、本を書いた著者と自分の間のコミュニケーションの構築です。読んでいる時にどうしても理解できなければ、時には感情に任せて、時には様々な方法を練りながら、「本という他者とケンカする」ことによって、自分と異なる発想を持ち、自分と違う土地に暮らし、あるいは自分と違う時代を生きた著者たちを、本気で理解するきっかけが生まれるはずです。
『読むことの力』には、15人の先生方による、本との付き合い方(あるいはケンカの仕方)が紹介されています。それぞれ専門の研究分野も異なり、深く付き合ってきた本の種類も違いますが、メッセージは一貫しています。一つ目はその文章を残した人々の環境やその文章を残した書き手の事情に思いを馳せることです。そして、もう一つは、読み手としてのその書物に向かう自分の立ち位置をどのように見定めるか、ということです。
本書で繰り返し紹介されるテーマに、世界の様々な場所で、中世のある時期までは、文章は基本的に口伝で、あるいは、耳で聞く(あるいは聴く)ことによって伝えられ、残されたという問題があります。古典的な詩文においては、「朗々と吟ずるように謡われた」のであるならば、私たちが通常選ぶ、黙読するようなスピードでは、書き手と同時代の人々がどのように理解し鑑賞したのかを理解できませんし、書き手が読み手に期待する意図が果たされないことになります。(林望「『読む』『聴く』そして『時間』」)『古事記』全編の注釈書を書いた本居宣長の『古事記伝』についての論考では、宣長が『古事記伝』を書いたのはある重大な懸念からだということが述べられています。文字を持たなかった古代日本の口伝文学であった『古事記』が、外来の中国語を使って文字に置き換えられ、書物となったことによって、オリジナルからどのように変わってしまったのか、について宣長がとらえた問題点に迫ろうという話題です。(神野志隆光「記紀を読むことのリアリティー」)また、庶民が文字を持たない時代から、文字を残す時代に移行する中世ヨーロッパにおいて「遺言」が残されるようになった背景から、当時の人々のどのような願いを受け止めることができるのかという、文書を残した中世の一般の人々の心に迫る問題も提起されています。(甚野尚志「中世の遺言が言い残したこと」)
本居宣長の論考を読むと、彼が『古事記伝』の著者であると同時に、『古事記』の読み手として重大な役割を果たしていることが窺えます。読み手の役割と書き手の役割の狭間にある人々の態度も、本書の重大なテーマです。この二つの立場を持つ代表的な人々が翻訳者と言えるのですが、文章が「書かれている内容」と「作家や話者が伝えようとしている雰囲気(トーン)」の両方を持つ以上、言語から言語への完全な置き換えは不可能です。この時、翻訳者は「書き手」の立場をとるべきか、「読み手」の立場をとるべきか。これまでの翻訳者たちが挑んだ様々な事例に、彼らの原著者の言葉に対する誠実な態度が見てとれます。(柴田元幸「翻訳者は『作者代理』か『読者代表』か」)また、宣長が行ったように、書かれている内容を字面通りに受け止めることが本当に正しいのかどうか、書かれたものの背景まで読み解くことによって、真実のメッセージを受け止め、紹介しようと試みることを、「資料(史料)批判」と言いますが、このような書かれたものに対する「批判」を新約聖書のイエスの奇跡物語を題材に考察した論考もあります。(大貫隆「奇跡の『心』」)非常にユニークな題材ですが、幕末から明治にかけて数多く表現された「美人図」に寄せる詩や散文についての論考では 、絵画の中の女性を鑑賞しつつ、そのイメージから紡ぎ出される情景や物語を書き残した男性たちの心情に著者は心を添わせています。 彼らは、当時出現し始めたばかりの写真は、鮮明であるだけに写し出すことができない何かがあると感じ、むしろ絵画に描かれた美しい女性たちに思いを馳せたのです。同じイメージ(図像)でも、欧米列強の世界侵略を物語る地図や軍艦図に殺気立つほどの敵意をかき立てた幕末の志士たちの中にもまた、絵の中の女性に「心を読み解く」文章を与えられた者が少なからず存在したことに驚かされます。ここには、絵の中の女性の心を読み解こうとした男性たちの心を読み解こうとする著者、という二重の「心を読む」構図も窺えます。(ロバート・キャンベル「読むことの苦楽ー『美人図』詩とその周囲をめぐって」)
つまるところ、読み手と書き手の狭間に立ち、書き残してきた人々は、等しく、書いた(描いた)人々や書かれた(描かれた)人々の心を、読み解こうとする努力を重ねてきたと言えるのでしょう。本を読むこととは、心を読むことにも繋がります。『読むことの力』は、他者の心を読む力、ひいては思いやる力を養う道具を、様々な形で私たちに与えてくれる本ということになります。だからこそ、書き手の置かれた時代や場所をはじめとする「書くこと」をめぐる環境への理解や、読み手としての自分の位置を見定める必要性が強調されるのです。書き手と読み手の間の、心と心のやりとりとなるからです。
さて、相手の心がわからない時はどうすれば良いのでしょうか。読書というのは時に非常に困難なものです。著者とのコミュニケーションの構築とは言いますが、著者が何を言いたいのかがわからない時というのも、少なからずあるでしょう。相手の言っていることを自分が完全に理解するためには、少なくとも、その話題に関する相手の「概念体系」(考え方の枠組み)というものを、読み手である自分が持っていなければなりません。もし、相手の話が自分の枠を超越していれば、現段階での私たちにそのまま相手の述べようとしていることを理解することは不可能ということになります。とりわけ哲学書などを読むときには、書き手の考え方の枠組みが、自分が持っているものよりも遥かに大きく深いものであることを、認めざるを得ない場面が繰り返されます。哲学者たちが人とは、人生とは、社会とは、と様々に問い続けた答えを、もし私たちが導こうとすれば、それは思考の経験や語彙の不足から、あまりにも幼く、単純なものになってしまうこともあるでしょう。これは、考え方の枠組みがまだ小さく、浅いということなのかもしれません。自分たちより、大きく深い枠組みで考え続けた哲学者たちの言葉が理解しづらいのは、この理由からであり、哲学者の言葉との出会いは、私たちが今持っている考え方の枠組みへの挑戦でもあります。
そんな時はどうすれば良いのでしょうか。二つの論考が、非常に近い答えを示してくれているように思います。一つは、解釈しようと努力することも、他者の解釈に頼って理解しようとすることも大切な道のりではあるが、今一度、わからないままに、それこそが本の深みであることを認めて、ただ本と「親しむ」態度に戻るというのです。読んでいる自分が「まだわからない」と気づくことで、深さを知るということも大切なのです。その態度こそが、更なる読書を後押ししてくれるのかもしれません。(門脇俊介「ダイモーンの声を聞くー哲学書を読む」)
しかし、このように自分を本に委ねてしまうというのは「本という他者とのケンカ」を放棄することにはならないのでしょうか。もう一つの論考では、自分の枠組みの中に書き手の言おうとしていることを無理矢理押し込めるのではなく、自分を能動的に書き手の「秩序のもとにすべりこませ」自分が変わろうとする、という発想が紹介されます。読み手の心を、書き手に委ねることで、読み手から書き手へ向かう心のつながりがここに生まれます。変わることができるかどうかもわからないあてのない旅になりますが、もし変わることができるのであれば、より「豊かな理解」が可能な自分への変化ということになるでしょう。その人生を選択するかどうかは、読み手次第です。ですが、変化が必ずやより豊かなものに向かうのかどうか。著者の終盤の言葉に、若い皆さんは勇気づけられることにもなるでしょう。(野矢茂樹「<意味の他者>を読む」)
もとより本書のすべての論考を紹介することはできませんが、上述した文章も、私が受け止めた書き手の心のほんの一部に過ぎず、「読むことの力」を身につけるためには、著者の先生たちの心を、皆さんが直接、受け止める以外にはありません。ゆっくり読むことや、わからないという事実を受け止めることも大切にしながら、本書を読んで欲しいと思います。編者のキャンベル先生も、最初は江戸時代の日本の文学と取っ組み合いのケンカをされたのだろうか、と想像するのは(大変失礼ながらも)楽しいものです。そうして、ご自分の枠組みを次第に豊かにされながら、その独自の枠組みを使って、ユニークな日本文学の紹介(それを「Jブンガク」と名付けていらっしゃいます)をされてきた道のりは、「読む」という旅を続ける限り、たとえ形が違ったとしても、皆さんもきっとたどるものとなるでしょう。なぜならば、「読むこと」とは他者を受け入れながら、自分の成長や変化と向き合うことであり、場所と時代を超えて、心を受け止める作業であるという点で、キャンベル先生の読書も、皆さんの読書も、変わるところがないからです。皆さんも、本から心を読み、心から心を橋渡しするコミュニケーションの世界の扉を、この一冊をきっかけに開いてみてください。